 懐かしいカオカ街道を往く。 右手にはイルファーロ郊外の果樹園がひろがり、低く刈り込んだ葡萄の木が整然と並んでいる。左手はなだらかな勾配の丘陵になっていて、春らしい若葉の緑色をした林がこんもりとひろがっている。その中に所々、開墾された小さな畑と農作業小屋が点在している。 このところルメイと二人でカリグラーゼの林ばかりに行っていたので久し振りに歩く道だ。荷は重いがまだ我慢ならないほどではなく、足取りも軽い。時おり丘から吹き降りる風が涼しい。 昨夜のことを考えながら歩いていたら、賭場にネバとイレーネらしい人物がいたことを思い出した。 「そうだ、ちょっとバタバタしてて伝え損ねてたけど、話しておきたいことがある」 果樹園の方を眺めていたルメイが振り向いた。 「昼飯のことかな」 フィアが声をたてずに笑ってルメイに肘をぶつけた。 「さっきあんなに食べたでしょ」 団欒に水を差すようで申し訳ないが、伝えておかねばならない事もある。 「ゴメリーがネバとイレーネを黒鹿亭に匿ってる」 ふざけていたルメイとフィアがさっと真顔になった。 「なんでそんなことが判る」 ルメイが怒っているような顔をして訊いてくる。 「昨日の夜、賭場で仮面をつけた男女とカードをした話をしただろう」 深夜にテーブルで話していた時、途中で寝てしまったルメイがふっと視線を流して、ううむ、などと唸っている。 フィアはその話を覚えていた。 「まさかその二人がそうだって言うの?」 「おそらく間違いない。小便をしに外へ出た時、その二人が後から連れだって出て来て話すのを隠れて聞いた。誰もいない場所でもネバと呼んでいたよ」 「でもそいつは自分でネバと名乗ったのでしょう? イルファーロの領主だって?」 「そうだよ。実に思い切った奴だ」 「それだけで決めつけるわけにはいかないんじゃないの?」 「あのな。ネバとイレーネは恋仲だ」 「え?」 フィアが眉根を寄せ、首をつきだした。 「要するに、物陰で口を吸い合ってたんだよ」 話が複雑になってフィアもルメイも黙り込んだが、誰も歩はゆるめない。周囲の果樹園が減って林ばかりになり、街の名残が失せた。 「仮面の女は眉間に刃物の傷があって、普段は剣を帯びているそうだ。それに、ネバと最近組んだという話をしてた。あれはイレーネだろう」 ルメイは何事か考えながら歩いていたが、静かに疑問を口にした。 「ネバに従ってる山賊たちはどうしてるんだろう。一人や二人じゃない筈だけど、まさか黒鹿亭にいるとは思えんが」 「……それは俺にも判らん」 フィアが背嚢の肩紐を押し上げながら、この話を信じたくないという顔をして俺を見る。 「さっき見た掲示板によれば、ネバは月に何度もチコルやデルティスで人を襲ってるみたいだけど、黒鹿亭に匿われてる身でそんなことが出来るのかしら」 ルメイとフィアに反論されているうちに判らない部分が増えてきたが、あの時の二人の様子からして確信は揺るがない。 「疑問は多いが、俺はあれがネバとイレーネだと思ってる」 カリーム、と言いそうになって軽く咳払いをした。 「グリムも同じことを言ってた」 「どういうこと?」 フィアが疑わしげな顔をする。 「グリムの隊商に護衛役の騎兵がいただろう。あいつらは本物のネバとやりあったことがあるらしい。それでグリムも、ネバがどんな奴か聞き及んでるわけだ」 「どんな奴なんだ」とルメイが問うてくる。 「手配書の似顔絵は似てない。どちらかと言えば端正な顔立ちで、普段から役者みたいに勿体ぶった口をきくって話だ。まさにそういう奴だったよ」 「手配書のネバは黒髪をざんばらに伸ばして、いかつい顔をしてたよな」 「ぜんぜん違う。仮面をつけてたから良くは判らんが、髪は栗毛で細面だった」 今更ながら、もう少しよく顔を見ておけば良かったと思う。ふと路傍の瓦礫が目に入った。周囲の土地から緑が減って灰色が増えている。カオカ方面は荒地が多く、この辺りから岩石や石が混じったガレ場が続く。 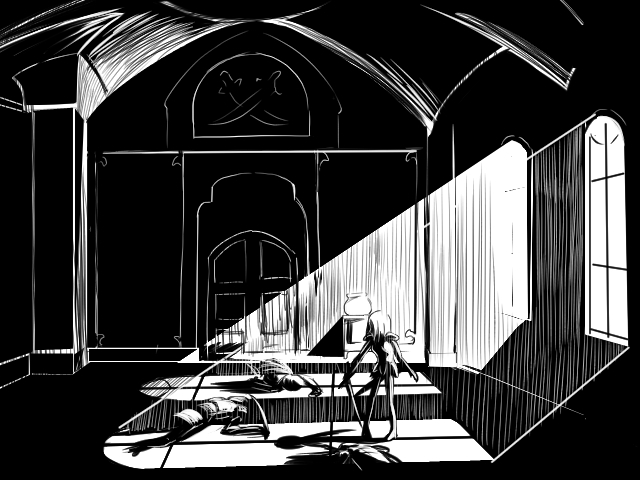 「イレーネはどんな女?」 与太話ではないのを判ってくれたのか、フィアは真面目な顔をしている。 「フィアよりは背が高かったけど、とても剣士には見えなかったな。女給のふりをしてたからドレスを着て、もちろん剣は吊るしてなかった。金髪で、額に傷があって、単刀直入に物を言う男勝りな奴だった。見た目はちょっとした美人だったがな」 二人とも俺の話に頷いている。やがてルメイが重い口を開いた。 「こんな近くに山賊が隠れてると思うとたまらんな」 「そうね。黒鹿亭のゴメリーも、碌な奴じゃなさそうね」 フィアの言葉に思わず考えさせられる。もし俺が言った通りだとしたら、ゴメリーはなぜ危ない橋を渡ってまで山賊を匿っているのだろう。その行為も吊るされるのに十分な罪状だ。 「だけど、それならこの近辺では悪さは出来ないってことね」 フィアの言う通りではある。 「いつか踏み込んで一網打尽にしてやりたくはあるがな」 そう言うと、ルメイはむっつりと黙り込んだ。知合いを殺されているのだから無理はない。 目印の石塔が見えてきた。 俺たちは立ち止まってそれを見上げた。カオカ遺跡の入口の近くに単独で造られた建造物で、一辺が人間の身長ほどもある直方体が積み上げてある。大昔にドラグーン人が造ったとされているが、地上から三つ目より上の部分は折れて倒れ、粉々になって周囲に瓦礫の層をなしている。何の目的で、どれほどの高さに造られたのかは判らない。石には文字らしきものが浮き彫りになっているが、風雨に削られ、苔に覆われ、ほぼ原形をとどめていない。カオカ遺跡へ行く者は、たいていこれを見上げて、この先にある紋様入りの石を積み上げて造った遺跡をまざまざと思い浮かべることになる。 「いつも何気なく見上げているけど、誰が何のために造ったのかしらね」 フィアがしみじみと言った。 「判らんが、運ぶだけでも恐ろしく手間がかかっただろうな」 巨大な石の構造物を黙って見上げていた俺たちは、誰からともなくまた歩き出した。  石塔を越えた辺りから上り坂になり、カオカ遺跡の手前でひらけた台地になっている。ここまで来ると巨大な二枚岩が見える。街で見た三階建ての建物ほどの大きさがあり、元は一枚の巨大な岩だったと思われるが、両手を開けば左右の岩に触れられる程度の隙間を開けて細長く向こう側に続く道が見える。 ここに初めて来た者はたいていそうする。二枚の岩の間の細道を通りながら、両手を左右に広げて壁を手さぐりしながら進むのだ。そしてその断面の滑らかさに驚く。これが自然に出来たとは思えないので一直線に切り通したのだと思うが、どうやって削ったのか見当もつかない。 「おお、朝からやってるなあ」 二枚岩で狩りをしている男たちが見えてきたので、ルメイが声をあげた。カオカの二枚岩と言えば相当の人気狩場で、ここを朝一番に使おうと思ったらそれこそ暗いうちにここまでたどり着いて場所取りをしなければならない。今、まだ朝も早いというのに既に狩りを始めているパーティーがある。 岩の細道の出口に大盾を持った剣士が一人、重心を低くして足場を固めている。コボルトをおびき寄せてきた釣り役が二枚岩から走り出て盾役の脇を通り過ぎると、コボルトが飛び出してくる。盾役はコボルトを体で受け止める。そこへ、コボルトからは見えない左右に分かれて待ち受けていた剣士たちが一斉に攻撃を加えて仕留める。これがいわゆる、カオカの二枚岩狩りと呼ばれる狩りだ。 二枚岩の前にいる大盾を持った男が、殲滅役の剣士にもっと下がれと命じている。待ち構えているパーティーとしては油断したコボルトにすんなり飛び出してきて欲しいところだが、いくら好戦的なモンスターとはいえ視界に沢山の人間が見えたらさすがに用心するからだ。 今、二人の剣士が細道の出口の壁に背をつけるようにして伏せ、さらにその外側に一人ずつ、合計四人の剣士が伏せている。盾役と剣士四人、それに釣り役が一人で合計六人の大所帯のようだ。場を仕切っている盾役の男が、おそらくリーダーのジェラール・マショーだ。ジェラール隊長は闘牛の牛よろしく、足が滑らないようにブーツの先で地面に窪みを付けている。 (→つづき) |
| 戻る |